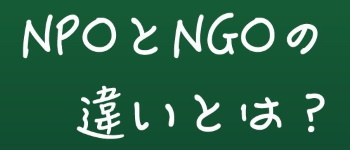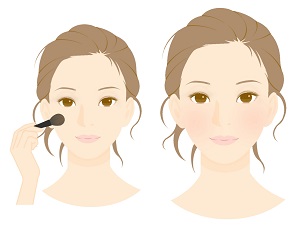日本で電話が開通したのはいつ?
東京 ― 横浜間で電話が開通したのは、1890年12月16日でした。
このため、この日は「電話の日」と制定されています。
当時の電話帳は冊子ではなく、一枚の紙だったそうです。
加入者が少なく、全員を並べても一枚の紙に収まったわけです。
その後、電話は急速に普及し、今では一家に一台どころか、一人がスマートフォンや携帯電話を複数所有するような時代になりました。
スマートフォンや携帯電話の電話帳機能で、相手を選んで電話できるので、相手の電話番号を覚えることも少なくなったでしょう。
電話番号が「0」から始まるのはなぜ?
ところで、電話番号は、たいていは「0(ゼロ)」から始まっています。
最初の「0」は何を示しているのでしょうか?
これは、「市外局番」と呼ばれている番号の最初の数字です。
固定電話は、通常「0XX-XXX-XXXX」といった形式の番号になっていますが、最初の「0」から始まるブロックが「市外局番」です。
東京都内から都内への発信など、同一エリアの相手と固定電話で通話をする際は、「市外局番」をつけません。
「0」から始まる最初のブロックをつけないのです。
反対に、同一エリアではない相手と通話するときには、「市外局番」をつけます。
つまり、「0」は同じエリア内の通話なのか、エリア外の相手との通話なのかを区別するための記号なのです。
「0」から始まる「市外局番」をつけて固定電話から発信すると、電話局にある交換機が「おっ、エリア外にかける電話だな」と判断して、相手の固定電話を探してつないでいるのです。
なお、「1」から始まる番号は、緊急性や公共性が高いサービスで、「110」が警察、「119」が消防、「177」が天気予報などと決められています。
ちなみに、スマートフォンや携帯電話の「090」、「080」は「市外局番」ではありません。
これらは、スマートフォンや携帯電話であることを示しているのです。
移動可能な電話は、どこから通話するかわからないので、これらには「市外局番」という概念はありません。
もっとも、通話先が固定電話であるときには、相手の「市外局番」が必要なのはいうまでもありません。