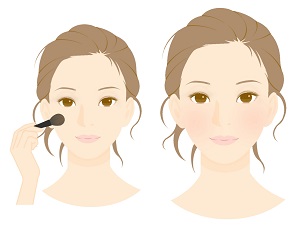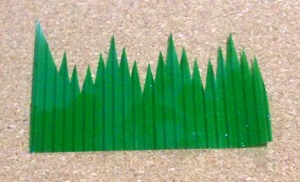「硬貨」と「紙幣」の不思議あれこれ
日頃使っている硬貨には製造年が刻印されていますが、紙幣には印刷されていないのはなぜでしょうか?
また、硬貨を造るときの原価はいくらなのでしょうか?
これらを順にみていきましょう。
硬貨にだけ製造年が刻印されているのはなぜ?
じつは、金本位制や銀本位制だった頃の名残なのです。
もともと硬貨は、明治時代に近代的な貨幣制度のもとで造られたものでした。
当時、金や銀は鋳造した年によって価格が変わるため、金貨や銀貨の硬貨に含まれる金や銀の量を明確にしていました。
いつ造った硬貨であるかを証明するために製造年が入っていたのです。
その後、金貨や銀貨を使わなくなってからもその慣習は残り、現在流通している硬貨にも製造年が入っているというわけなのです。
ちなみに、紙幣にも製造年は入っています。
ただし、それはアルファベットと記号を組み合わせたもので、日銀だけにしか製造時期がわからないそうです。
ところで、硬貨を造るときの原価がいくらかご存知でしょうか?
硬貨を造るときの原価は?
硬貨を造るときの原価は、製造年により変動があると思われますが、概略次のようにいわれています。
- 500円玉: 30円
- 100円玉: 25円
- 50円玉: 20円
- 10円玉: 10円
- 5円玉: 7円
- 1円玉: 3円
なんと、1円玉と5円玉は2円の赤字なのです。
さらには、紙幣を造るときの原価をご存知でしょうか?
紙幣を造るときの原価は?
紙幣を造るときの原価は、製造年により変動があると思われますが、概略次のようにいわれています。
- 1万円札: 22円
- 5千円札: 21円
- 2千円札: 16円 (最近ではあまり見かけませんが)
- 千円札: 15円
このように、紙幣はかなり安く造れるのです。
なんと、1万円札や5千円札を造るよりも、500円玉や100円玉のほうが原価が高くつくのです。
いずれにしても、額面と原価との差額はどこへ行っているのでしょうか?
貨幣の額面と原価との差額は、政府の貨幣発行益となるようです。
ついでに、硬貨のどちらが表かご存知ですか?
硬貨のどちらが「表」?
硬貨のどちらが「表」で、どちらが「裏」なのでしょうか?
「500」とか「100」などの英数字で金額が大きく表示されている方が「表」のような気がしますが、じつは「五百円」とか「百円」などの漢数字で小さく表示されている方が「表」で、年号が表示されている方が「裏」なのです。
何となくわかりにくいですが、お手元にある硬貨をながめてみてください。
ちなみに、以下のものがすべて「表」です。